 天文
天文 プラネタリウムの歴史とは? わかりやすく解説!
プラネタリウムの歴史世界で最初にプラネタリウムをつくったのはドイツのカール=ツァイスという光学会社のバウエルスフェルト博士です。これが、はじめてミュンヘンの博物館に取り付けられたのは1923年10月のことでした。それに引き続きドイツ各地でつ...
 天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文  天文
天文 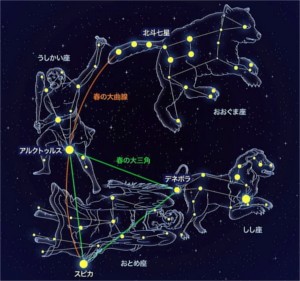 天文
天文  天文
天文