 エネルギーと原子の研究
エネルギーと原子の研究 斜面の法則とは? エネルギー保存の法則とは?
夢からうまれた斜面の法則大昔から人類は「少しでも楽に仕事をしたい」という夢を抱き続けてきました。この夢は「永久機関」をつくろうという努力にかわりました。(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).pus...
 エネルギーと原子の研究
エネルギーと原子の研究 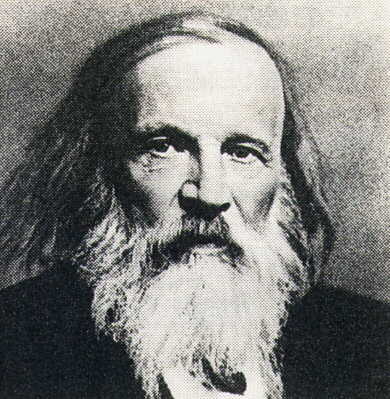 物質の研究
物質の研究  物質の研究
物質の研究  物質の研究
物質の研究  物質の研究
物質の研究 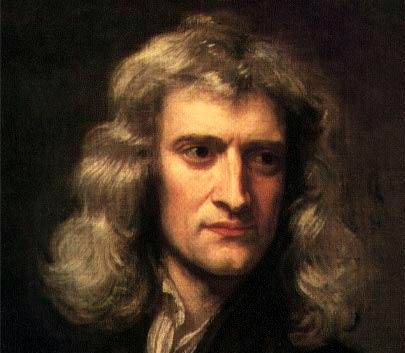 新しい科学の誕生
新しい科学の誕生 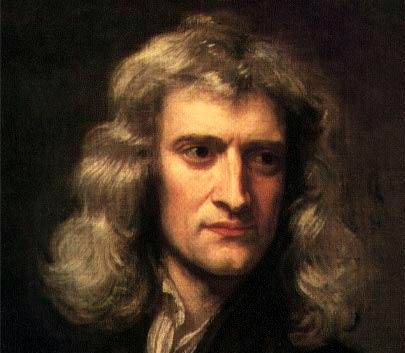 新しい科学の誕生
新しい科学の誕生  新しい科学の誕生
新しい科学の誕生 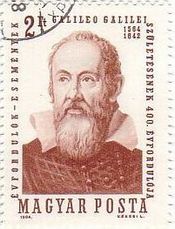 学問の誕生
学問の誕生 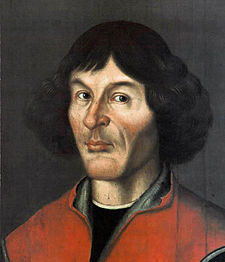 学問の誕生
学問の誕生 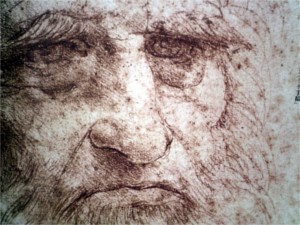 学問の誕生
学問の誕生  学問の誕生
学問の誕生  学問の誕生
学問の誕生 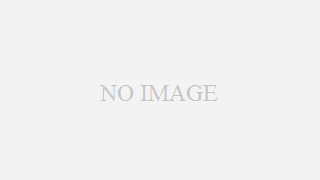 学問の誕生
学問の誕生  学問の誕生
学問の誕生  学問の誕生
学問の誕生  学問の誕生
学問の誕生 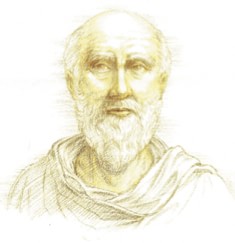 学問の誕生
学問の誕生  学問の誕生
学問の誕生  学問の誕生
学問の誕生